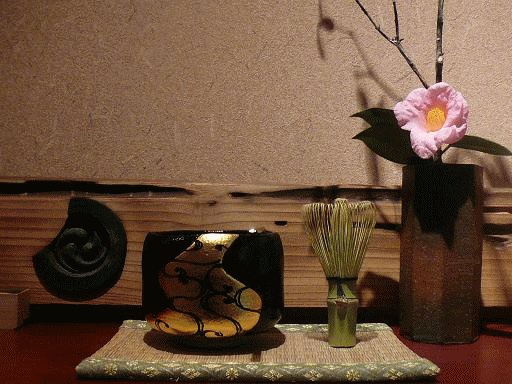しし)”とだけ表現した。ところが、魚については、セイゴ→ フッコ→スズキのような出世魚が存在する。その国の文化・風 土により語彙(ボキャブラリー)数が豊富になる。とても興味 深い。
因みに、茶の湯で「茶」の字を分解して「草・人・木」と表 現し意味合いをつけているのだが、本来は的外れ。「茶」の字 は新しいのだ。
日本の茶産地では、早く摘むチャを“茶”、遅く摘むチャを “茗(めい)”と呼ぶ地域があった。茶は椿(ツバキ)の仲間 なので冬に開花する。
茶葉に栄養分を残す為、夏過ぎて開花の後、結実して養分を 消費させないように、そして翌春の茶摘みの時、作業し易いよ うに枝を整える。その時に刈った育ち過ぎた葉を飲用に加工し たものが晩茶(ばんちゃ)。晩い(おそい)という意味だ。何 故、字が“番”茶でないのか。その理由を含め、美味しいお茶 の原理と共に次回説明しよう。